丸窓と縁側のデザインとは?和室の魅力を高める意匠と機能性を両立する
2025.9.8
こだわり
Earnest architects

高級住宅を建てる際に「和室を設けたい」とお考えになる方は多くいらっしゃいます。和室のデザインの中でも、特別な存在感を放つのが「丸窓」であり、古くから寺院や茶室などで採り入れられてきた意匠です。また、和室と庭を緩やかにつなぐ「縁側」も、日本建築ならではの趣を残しながら、現代の暮らしに心のゆとりをもたらす空間です。
本記事では、これら丸窓と縁側の概要や魅力、注意点と活用方法、実例もご紹介します。和室のある住まいや、暮らしに趣と心地よさを求める方は、ぜひ参考にしてください。
目次
丸窓とは?

丸窓とは、円形に切り取られた窓のことを指し「円窓」とも呼ばれています。鎌倉時代、禅宗様(唐様)と共に中国から伝わり、日本の寺院建築や茶室、数寄屋造りなどに広がりました。塗り壁に映える丸窓は、単なる採光の役割にとどまらず、精神性や美意識を象徴する存在として受け継がれてきました。
代表的な例として、神奈川県鎌倉市の明月院では、丸窓越しに望む本堂後庭園の四季折々の景観が多くの人を魅了しています。また京都府にある源光庵では「禅と円通」の心を表現した丸窓があり、その円は大宇宙を象徴するとされています。
現代においても、和室に丸窓を採り入れることで空間に奥ゆかしさをもたらします。歴史・宗教的な背景から離れ、デザイン性の高い住宅の要素として採用されるケースも増えており、伝統とモダンの両方に調和する魅力を備えています。
和室で丸窓を採り入れるメリット

和室の丸窓は、意匠性を高め暮らしに情緒や余韻を感じられます。外観へのアクセント効果や採光性の高さ、四季の景色を切り取る楽しみなど、丸窓ならではの魅力が日常に上質な時間をもたらします。ここでは、和室に丸窓を採用する具体的なメリットをご紹介します。
外観のアクセントになる
住宅の窓といえば四角形が一般的であり、壁や床、外壁も直線的なラインで構成されることが多いです。その中に丸窓を採り入れると、曲線の柔らかさによって建物全体のデザイン性が高まります。
丸窓は和室の要素でありながら、直線で構成されがちな住まいのアクセントとして機能し、一般的な住宅とは異なる洗練された雰囲気に導きます。
四季折々の変化を楽しめる
丸窓は、まるで絵画の額縁のように景色を切り取る役割を果たします。四角い窓では得られない視覚的効果によって、日常の風景を芸術的に切り取ります。四角い窓よりも余分な情報がそぎ落とされ、景色がより印象的に際立ちます。直線窓にはない柔らかさがあり、四季の移ろいや光を象徴的に感じさせ、日常の眺めを詩情豊かに演出してくれます。
和モダンと相性が良い
丸窓は伝統的な和室に採り入れられてきた要素ですが、現代的な住まいにも相性が良いです。特に「和モダン」スタイルでは、古来の和風デザインとスタイリッシュなモダン要素を融合させることで、落ち着きと洗練さを兼ね備えた空間を実現できます。
丸窓を採り入れると、シンプルな和室にデザイン性が加わります。伝統の意匠を継承しながらも現代的な美意識を映す要素として、丸窓は洗練された空間づくりにふさわしい選択肢の一つです。
防犯性能が高い
丸窓は多くの場合「はめ殺し」という手法で設計され、開閉ができない仕様になっています。そのため、鍵がなく侵入経路として狙われにくいという特徴があります。窓ガラスを割られない限り、不審者の侵入を防ぎやすい点もメリットです。丸窓は一般的にサイズが小さく、人が侵入しにくいため一般的な四角窓より防犯性は比較的高いといえます。
採光性に優れている
丸窓は形状が円形のため、光を柔らかく拡散させる効果があります。直線的な窓に比べて広い角度から光を取り込み、部屋全体を明るく包み込むように照らします。
時間帯によって光の表情は移ろい、朝には清らかな光が差し込み、夕暮れには柔らかな光に包まれるひとときを享受できます。
丸窓にかかる費用・期間

丸窓は独特の美しさを持つ一方で、費用や工期の面では四角窓に比べて負担が大きくなりがちです。まず、既製品の種類が少なく、特注対応となる場合が多いため製品代が高くなります。加えて、ガラスやサッシを円形に加工するには手間がかかり、部材費も上昇します。取り付け工事においても、円形の枠を正確に納めるには高度な技術が必要で、調整や仕上げに時間を要することから施工費が割高になり、工期も延びる傾向があります。これらの要素が積み重なることで、丸窓は同じサイズの四角窓に比べて高額です。コストや工期についても事前に把握しておくことが大切です。
丸窓を採り入れる際のポイント
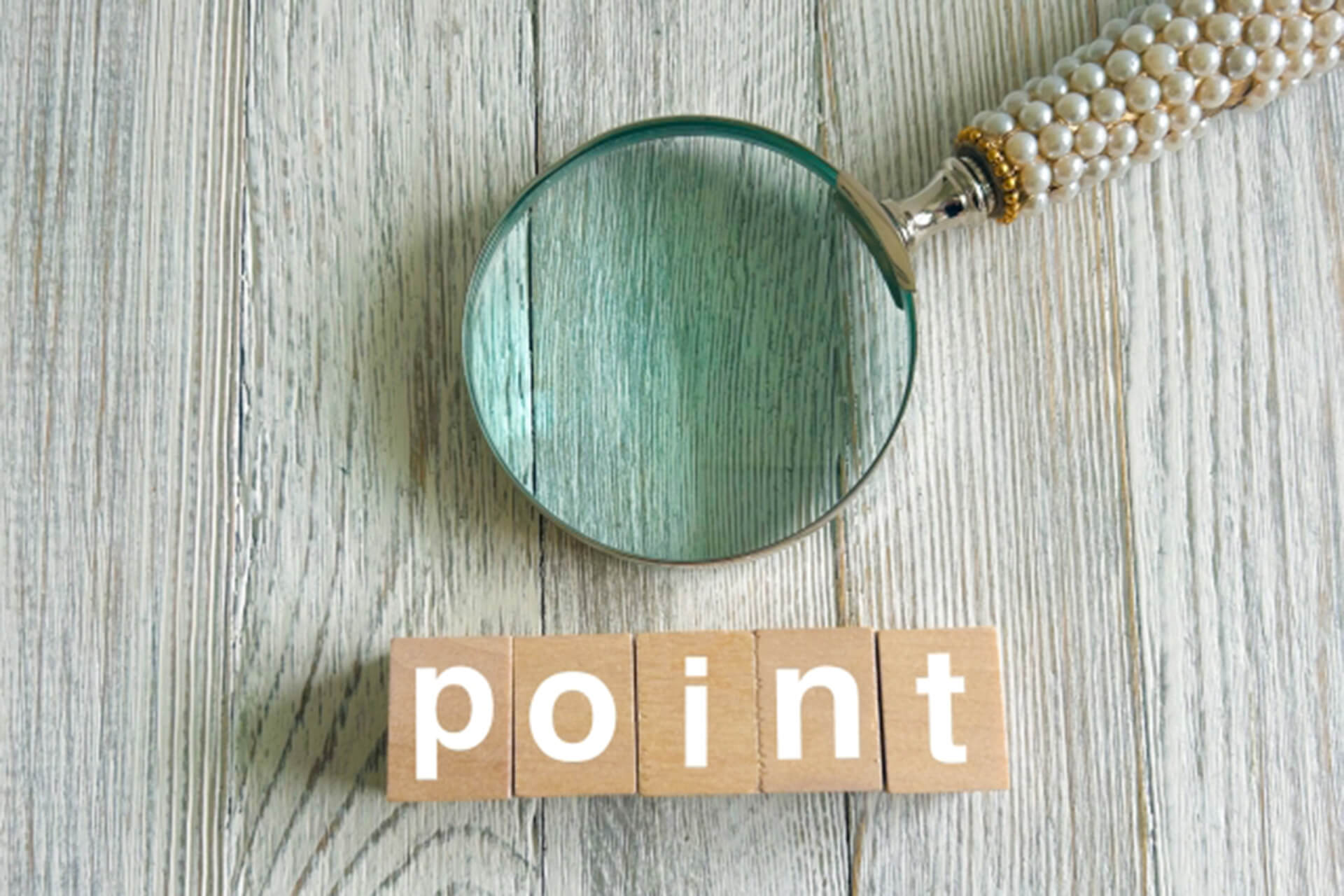
丸窓を採用する際にはデザイン性だけではなく、実用性や維持管理の観点も考慮することが大切です。ここでは、丸窓を採り入れる際に押さえておきたい4つのポイントをご紹介します。
また、和室の実例は下記からご覧いただけます。
高さを工夫する
丸窓は設置する高さによって、空間に与える印象が大きく変わります。畳に直接座って過ごす和室では視線が低くなるため、壁の中心から下に丸窓を設置することで視界に入りやすくなり、存在感を際立たせられます。一方、ソファや椅子を用いるタイプの空間では、壁の中心より上に丸窓を設置すると開放感が生まれます。
住まいの過ごし方に合わせて設置位置を工夫することが、丸窓を生かすための鍵となります。
ガラスにもこだわる
丸窓をより個性的に演出するためには、窓に使用するガラスの種類を選ぶことも重要です。一般的な透明ガラスだけではなく、表面に凹凸を施したデザインガラスや、彩りを加えたステンドグラスを用いると、光の表情が変わり特別な空間を演出できます。
ガラスそのものがインテリアのアクセントとなるため、和室や外観の個性を際立たせる効果も期待できます。
定期的にお手入れが必要
丸窓の美しさを長く保つには、素材ごとに適切にお手入れをすることが必要です。木製枠の丸窓の場合は、柔らかい布でほこりを拭き取り、年に1〜2回は専用のワックスやオイルを薄く塗布すると、艶や耐久性を維持できます。
紙障子を用いた丸窓の場合は、専用クリーナーで軽く拭くと汚れが落ちやすく、全体が古くなった際には2〜3年ごとの張り替えが理想です。
金属枠の丸窓の場合は素材に合わせたケアが求められ、アルミは水拭きと乾拭き、真ちゅうやブロンズは専用クリーナーでの拭き取りが必要です。さらに年に2回程度、金具の緩みやシーリング材の劣化を点検することで、不具合の早期発見につながり、長持ちさせられます。
冷気・結露対策をする
丸窓はカーテンを取り付けないことが多いため、冬場には冷気が入り込みやすく、結露が生じやすい点に注意が必要です。特に結露は木材の腐食やカビの発生を招くため、対策が欠かせません。
断熱性を高める方法として、既存の丸窓の内側にガラスやアクリル板を追加した二重窓にする工夫があります。これにより外気の影響を大幅に軽減可能です。また丸窓の周囲に調湿素材を用いた壁を設けることで、湿度を調整し快適な環境を維持できます。
和室と庭をつなぐ「縁側」とは?

縁側とは、日本の伝統的な住まいに見られる、和室と庭の間に設けられた半屋外空間です。室内にいながら自然を身近に感じられる場所であり、日常の移動や休憩、作業スペースとしての使用、来客との談笑の場として使われるほか、多様な役割を果たせます。単なる通路ではなく、日常のひとときを豊かに彩る特別な空間といえます。
室内と屋外のつながりを演出し、開放感や心地よい居住性を高めることができます。伝統的な縁側の設計思想は、自然との調和を重んじる日本建築の魅力を今に伝える存在です。
縁側の魅力

縁側は単なる腰掛けや通路ではなく、暮らしにさまざまな価値をもたらす空間です。自然とのつながりを感じながら、室内環境を快適に整え、家族や友人との交流を豊かにする役割も果たします。ここでは、縁側の持つ主な魅力をご紹介します。
夏は涼しく冬は暖かく過ごせる
縁側によって外と室内の間に空間ができるので、断熱効果や遮熱効果を期待できます。冬は暖かい空気が逃げにくく、冷たい空気は直接入り込みにくくなります。夏は室内の冷気が外に漏れにくく、室温の上昇を抑えられます。その結果、冷暖房の効率が高まり、快適で環境にも優しい暮らしを実現可能です。
さらに縁側を設けていると、ひさしが影を作ってくれるため直射日光が部屋に入りにくくなり、夏場は暑さを感じにくくなります。縁側は日本の気候風土に適した、理にかなった空間設計といえます。
庭の風景や借景を楽しめる
縁側に腰を下ろせば庭の草花や木々を間近にして、心を落ち着けるひとときを過ごせます。障子や木枠の窓越しに四季折々の景色を切り取り、光や影の変化を感じながら庭木や山並みを借景として取り込みます。室内にいながら自然の広がりを体感でき、暮らしに豊かな情緒をもたらします。家と外部環境の調和を楽しむことが可能です。
現代住宅でも、ウッドデッキやテラスを通じて縁側のような視覚的・心理的つながりを取り入れています。
室内を広く見せる効果がある
縁側と居室の床の高さを揃えることで、空間がひと続きになり、室内を広く感じさせる効果があります。さらに床材や内装の雰囲気を統一することで、より奥行きと一体感が強調されます。障子やふすま、ガラス戸を開け放つと、視線が庭へと抜けて開放感が生まれ、住まい全体が広々とした印象になるのも魅力です。
コミュニケーションが取りやすい
縁側があると、日常的に家族とのコミュニケーションが自然に生まれます。半屋外の縁側は室内と庭をつなぐ境界に位置するため、庭で過ごす家族とも、室内で過ごす家族とも交流が可能です。通路としての機能も兼ねているため、室内の移動の際に声をかけたり、縁側に腰を掛けてその場で談笑もできます。また、庭で遊ぶ子どもやペットを見守りながら作業を続けることもでき、縁側でお茶を飲みながら語らえば、自然と会話が弾み、和やかな時間が流れます。このように縁側は多用途で、家族の日常にさまざまなコミュニケーションの場をもたらします。
縁側を設ける際に押さえておきたいポイント

利用目的や庭との調和を事前に整理しておくことで、実際の暮らしに適した縁側を実現できます。ここでは、縁側を設置するに当たって押さえておくべきポイントをご紹介します。
縁側を設置する目的を明確にする
多用途な縁側ですが、目的を明確にしておくことは大切です。
家族とのコミュニケーションの場として活用したい場合、家の奥にある和室に縁側を設けても十分な効果は得られません。コミュニケーションを重視するなら、家族の動線上に和室を配置したり、勝手口付近に縁側を設けたりするなど、用途に応じた設計が求められます。目的が曖昧なまま設計すると、使われずに無駄な空間になりかねません。事前に具体的な使い方を想定しておき、暮らしに合った縁側を計画しましょう。
縁側と庭のバランスを考える
縁側の設置によって庭が狭く感じられることもあります。庭に面する和室の奥行きと庭の広さが同程度であれば、縁側が自然に溶け込み、全体として調和の取れた住まいとなります。
また、庭に配置する草木や石、水盤といった要素と縁側の素材やデザインを調和させることで、統一感ある空間が生まれます。縁側は単独の要素としてではなく、和室や庭と併せて計画することで、その魅力を最大限に引き出せます。
アーネストアーキテクツが手掛けた施工事例
建築設計事務所のアーネストアーキテクツは、伝統的な丸窓や縁側といった意匠を現代的な住宅デザインに活用した住空間を数多く手掛けています。ここでは、その代表的な施工事例を3つご紹介します。
グレーの濃淡


住まいのアクセントとして丸窓を用いたデザインです。杉板を転写したコンクリート打ち放ちの壁面に開いた丸窓から光が漏れ、まるで満月のような情緒を演出した外観デザインです。エントランスを進むと、一段下がった位置に設けた和室があり、ゲストルームを兼ねる「離れ」のようなつくりとしました。和室からは池を配した和庭園を眺めることができる、和モダン住宅です。
前衛的なモダンデザイン


丸窓を用いたモダンな住まいは、伝統と革新が響き合う空間です。和室は、コンクリート打ち放しの壁と畳・障子を採り入れました。丸窓からは瑞々しい楓を眺められ、春は新緑、秋は紅葉と四季の彩りを室内に映し込みます。無駄を削ぎ落とした前衛的な設計は光や影をもデザインの要素とし、特別な空間を創出します。
街並みに浮かびあがる白い家


この住まいはシンメトリーを基本とし、白い壁にアイアンを組み合わせたデザインがクラシカルでエレガントな印象を与えます。その中央に据えられた丸窓には、海の灯台をイメージしたステンドグラスをはめ込み、象徴的な存在としました。室内では奥様のアトリエへとつながるホールに位置し、洋風デザインに丸窓を調和させた好例となっています。
外部空間とのつながりを深める「縁側」の設計と活用法

丸窓や縁側は、日本の住まいが育んできた、内と外をやわらかくつなぐための機能性と意匠性を備えた要素です。
現代のライフスタイルにおける縁側は、多目的に使える柔軟な空間として、その価値が改めて見直されつつあります。アウトドアリビングやテラス、デッキなど屋外空間を積極的に暮らしに取り込む住まいが増える中で、室内でも屋外でもない「中間領域」としての縁側が、心地よい居場所として注目されています。自然の光や風、庭の気配を感じながらも、天候や視線の影響を受けにくい縁側は、現代の暮らしに適した緩衝空間といえます。
また、庭との一体感を高めるためには、素材選びと床面の高さの工夫が求められます。
縁側の床材には、無垢材や質感のあるタイルなど、屋内外どちらにもなじむ素材を選ぶことで、空間の連続性が生まれます。床の高さは腰を掛けた際の姿勢や視線の高さ、室内から縁側へ、縁側から庭へと移る際の動作に無理が生じないことが重要です。
住まいの意匠性には、採光や通風をコントロールする開口部や建具のデザインが欠かせません。丸窓はやわらかな光を室内に取り込みつつ、視線を適度に遮る効果があり、落ち着きのある縁側空間を演出します。引き戸や障子、格子戸などを組み合わせることで、季節や時間帯に応じた光と風の調整が可能となり、内と外が心地よく溶け合う住まいが完成します。縁側と丸窓を住まいに取り入れることで、日常の中に外部(庭)を感じられる空間が生まれます。
和モダンデザインで際立つ丸窓の「意匠」と機能性
丸窓は、和の伝統的な意匠を継承しながら、現代住宅に新たな表情をもたらします。直線で構成されがちな空間に円という形状を取り入れることで、和モダンならではのやわらかさと奥行きが生まれ、象徴的なデザインとなります。
丸窓のサイズや配置は、空間に与える心理的な効果を左右します。大きな丸窓は開放感と象徴性を高め、空間の主役として強い印象を残します。一方で、やや抑えたサイズの丸窓は、落ち着きや余白を感じさせ、視線を自然と外へ導く効果があります。床に座る、腰掛けるといった居場所との関係を踏まえて高さや位置を定めることで、丸窓は単なる開口部ではなく、空間体験を支える重要な要素となります。
プライバシーを確保しながら光を取り込むガラスには、すりガラスや和紙調ガラス、型板ガラスなどがあります。外部からの視線を遮りつつ、やわらかな自然光を室内に導くことができます。直射光を抑えた光の入り方は、空間に陰影を生み、和モダンデザインの魅力をより一層引き立てます。
また丸窓は、季節の移ろいや自然の表情を切り取る「フレーム」としての役割も担います。新緑や紅葉、雨に濡れる庭、揺れる木々の影といった風景を、一枚の絵のように室内へ取り込むことで、住まいの中に静かな情緒が生まれます。意匠性と機能性を兼ね備えた丸窓は、和モダン住宅において、暮らしの質を高める重要なデザイン要素となります。
和室空間の「安らぎ」を演出する照明計画のテクニック

和室における照明計画は、空間を明るくするための装置ではなく、光と影の関係を整える設えとして捉えることが重要です。丸窓や障子と呼応する柔らかな光が、和室ならではの静けさと奥行きをつくり出します。
丸窓や障子のある和室では、間接照明とフットライトが活躍します。天井面や壁面をなぞる間接照明で直接光を避け、反射光で空間を満たすことで、丸窓の輪郭や障子越しの光が際立ちます。足元にはフットライトを組み合わせ、夜間の安全性を確保しながら、床面に低い光のレイヤーをつくることで、視線が自然と落ち着く構成となります。
陰影の美しさを引き立てるためには、光の色温度と強さの調整を行います。色温度は電球色を基本とし、過度に明るくしないことで、素材の質感や陰影が浮かび上がります。時間帯や用途に応じて調光できる計画とすることで、昼と夜で異なる表情を楽しめる和室となります。
和の雰囲気を高めるデザイン性の高い照明器具の選び方
●和紙や布、木など、光を透過・拡散する素材を用いた器具を選ぶ
●形状は球体や円筒など、丸窓や障子と呼応する柔らかなフォルムを意識
●装飾性を抑え、構造や素材感が際立つシンプルなデザインとする
●天井照明だけでなく、行灯やブラケットなど低い位置の光源を取り入れる
●器具単体で主張させるのではなく、建築や空間に溶け込む存在感を重視
こうした照明計画によって、和室は単なる部屋ではなく、光に包まれた「安らぎの場」として成立します。光の扱い方そのものが、和室の質を決定づける要素となります。
丸窓と縁側を最大限に活かす間取り設計のアイデア
丸窓や縁側を住まいの魅力として最大限に引き出すためには、個々の意匠だけでなく、空間同士の関係性を組み立てる間取りが求められます。視線の流れや居場所の重なりを意識することで、住まい全体に奥行きと静かな豊かさが生まれます。
リビングやダイニングから和室を美しく見せる配置は、正面に据えるのではなく、少し角度を振った配置や視線が抜ける位置関係をつくることが効果的です。扉や建具で完全に仕切らず、引き戸や障子を介して緩やかにつなぐことで、空間の連続性が高まります。
また、丸窓と視線が抜ける計画は、空間の広がりと奥行きを生み出す要素です。縁側越しに庭を望み、その先に丸窓が重なる構成とすることで、視線が幾重にも重なり、実際の面積以上の広がりを感じさせます。丸窓は単なる開口ではなく、視線を導く装置として機能し、住まいの中に静かなリズムを与えます。
丸窓や縁側の向きは、敷地周辺の環境や光の入り方に配慮して配置します。庭の見せ場や借景となる緑、空の抜けを意識して丸窓や縁側の向きを定めることで、季節や時間帯によって異なる表情を楽しめる住まいとなります。
和室の魅力を引き立てる「現代的な素材」の融合
木材、和紙、土壁といった伝統素材にコンクリートや金属、ガラスといった無機質素材を点在させることで、現代的な緊張感や洗練された雰囲気が漂います。素材同士をなじませるのではなく、質感や反射、重さの差を意識して配置することで、互いの素材感が際立ち、和モダンらしい構成が立ち上がります。
和室の統一感を高める家具やインテリアのコーディネートは、床座を前提とした低めの家具や、装飾を抑えたシンプルな意匠を選ぶことで、畳や建具の水平ラインが強調され、空間に静けさが生まれます。色数を抑え、木部や壁仕上げとトーンを揃えることで、和室全体が一つの設えとしてまとまります。
また、現代の和室には日常使いに耐える実用性が重視されます。耐久性の高い和紙クロスや、汚れやひび割れに配慮した左官材、反りや割れを抑えた加工木材などを選定することで、意匠性を保ちながらメンテナンスの負担を軽減できます。素材の美しさを時間とともに楽しめること。その前提となる耐久性への配慮が、現代的な和室を成立させる基盤となります。
デザイン性の高い丸窓と縁側を採り入れよう

丸窓と縁側はいずれも、日本建築における空間の質を高める重要な要素です。丸窓は、和室に特別な趣を添えるだけでなく、外観デザインにアクセントを与え、四季の移ろいを切り取る装置として機能します。その一方で、コストや外部からの視線などに配慮し、設計段階から適切に計画することが不可欠です。
縁側もまた、和室と庭をつなぐ緩衝空間として、光や風を取り込みつつ暮らしを豊かに彩ります。外部との連続性を生み出し、季節感や団らんの場を提供する点で極めて有効ですが、敷地条件や庭とのバランス、維持管理への考慮が求められます。両者を適切に取り入れることで、日常に上質な体験をもたらす住空間が実現します。
アーネストアーキテクツは、「高級注文住宅」を得意とする建築設計事務所です。
丸窓や縁側といった日本の伝統的な要素を現代的に昇華させ、意匠性の高い住宅デザインを得意としています。和室や縁側、印象的な丸窓を取り入れた住まいをご検討されている方、伝統とモダンを融合させた住まいをご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。






